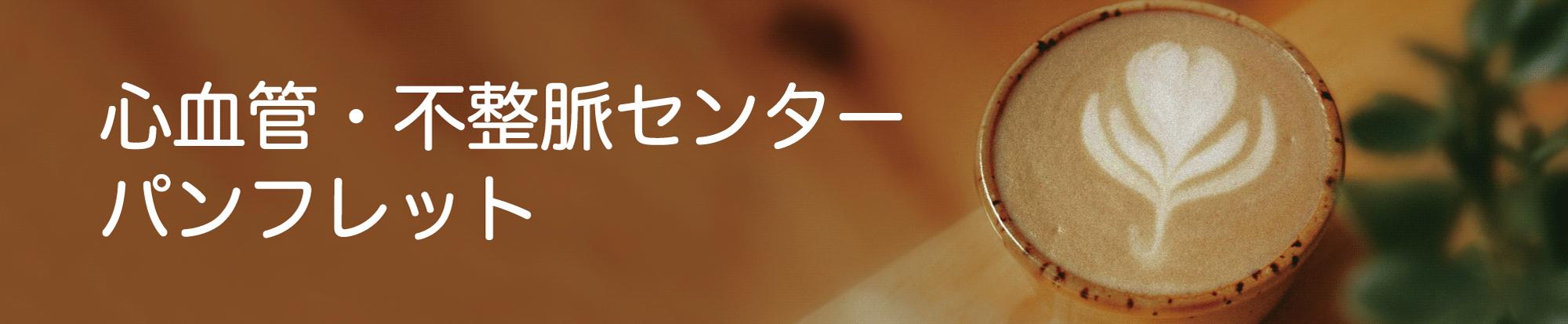循環器内科
北斗病院
これまでの経験を活かして地域の循環器診療に貢献します
循環器専門医、日本心臓血管インターベンション学会認定医、不整脈専門医、救急専門医が常勤で勤務していますので、心臓血管系のあらゆる疾患に対応が可能です。循環器系のあらゆる疾患に対して最適で最新の治療を提供してゆきます。
当科の紹介
2020年4月に私が東京から当院に着任し、現在の循環器内科をまとめています。心臓血管センターの中心となっていた医師が2019年までに全員退職してしまい循環器診療の継続が困難となったため、私が北斗病院へ赴任しました。
心臓血管外科部門では2019年から北里大学心臓血管外科がチームで新たな心臓血管外科診療をスタートさせていましたが、循環器内科部門では残っていた数人で何とか診療を継続するという状態でした。当時、新たに北斗病院の循環器内科をまとめることができる人材を全国で募集していたようで、私は東京の病院に勤務していたところ人材派遣会社より声が掛かりました。
私は東京女子医大病院循環器内科に所属し、女子医大病院の関連施設にある地域の循環器センターで長く仕事をしてきました。このお話を頂いた際、一つの病院の循環器部門をすべて任され、地域医療に貢献する、今まで私が行ってきた仕事の集大成として定年退職まで医師として残りのキャリアには悪い話ではないと考えました。子供たちが親の手を離れる年齢となったタイミングでもあり赴任することを決めました。幸い、当院に残って循環器診療を続けていた、赤津先生、高橋先生、沼崎先生も私の循環器診療のあり方に共感をいただき、私を中心に一つのチームとして循環器内科診療を新たにスタートさせることができました。
残念ながら、赴任時期がコロナ禍と重なってしまい、通常の診療体制や活動が制限される状況でのスタートとなりましたが、2023年からはようやくコロナの影響がない状況で活動ができる状態となりますので、心臓血管外科ともタッグを組み、新しい北斗病院循環器チームとして地域の循環器診療に貢献したいと考えています。
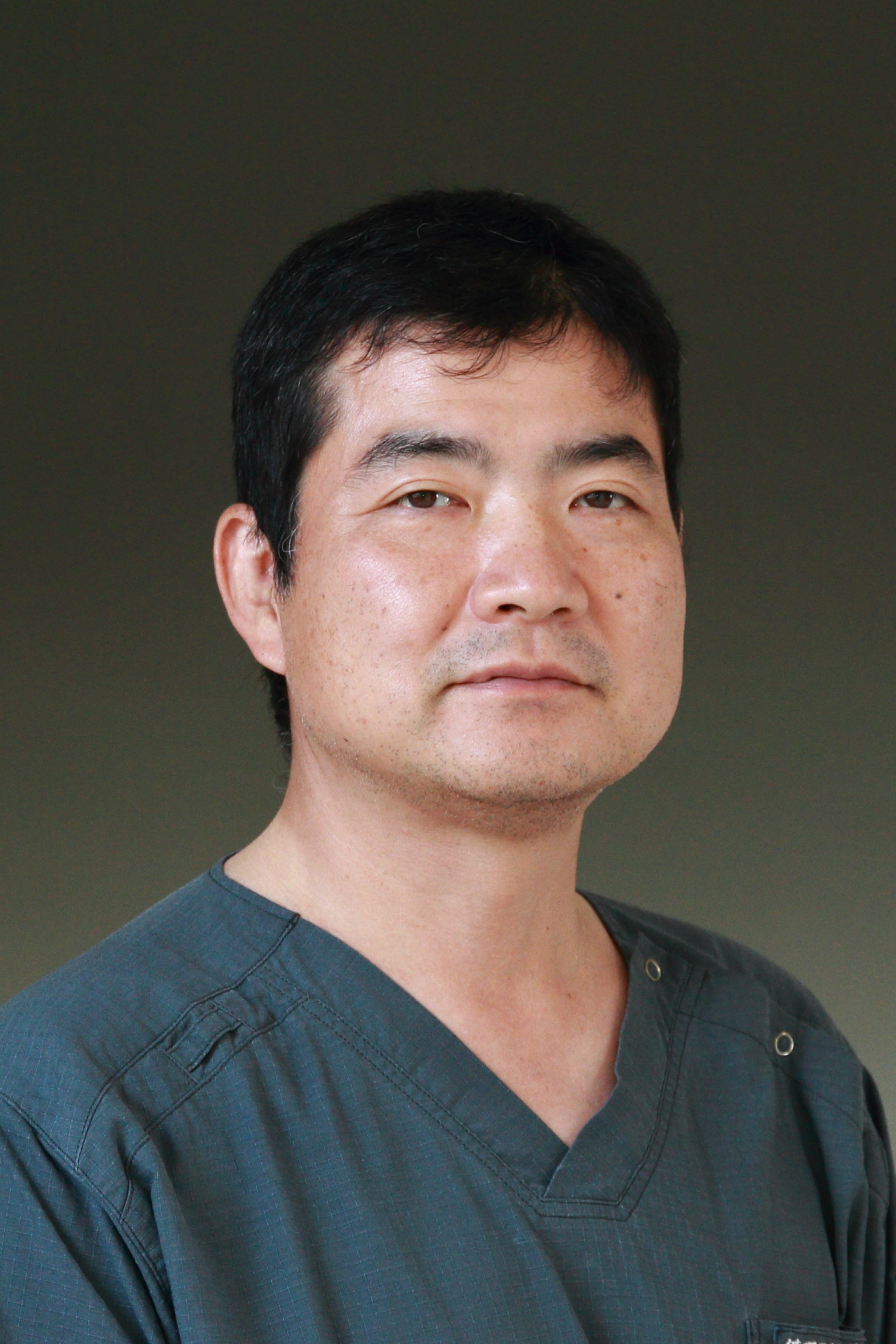
循環器内科部長
心血管・不整脈センター センター長
遠田 賢治
受付・診療時間
- 2023年06月02日更新
- 循環器内科予定表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 |
遠田 |
遠田 |
赤津 |
沼﨑 |
||
| 午後 |
高橋 |
高橋 |
高橋 |
赤津※1 |
【受付時間 】
月・水・木/8:00~11:30、12:00~16:30
火/12:00~16:30
金/8:00~11:30
【診療時間 】
月・水・木/9:00~ 12:00、13:00~17:00
火/13:00~17:00
金/9:00~ 12:00
※ 循環器内科は予約制です
※1:第2・第4木曜のみ診察
再来患者様 予約対応時間:月~金 14:00~17:00(電話:0155-48-8000)
医師紹介
-

-
遠田 賢治
循環器内科 部長 / 心血管・不整脈センター センター長
-

-
高橋 一泰
循環器内科 医長
-

-
沼﨑 太
循環器内科 医長
-
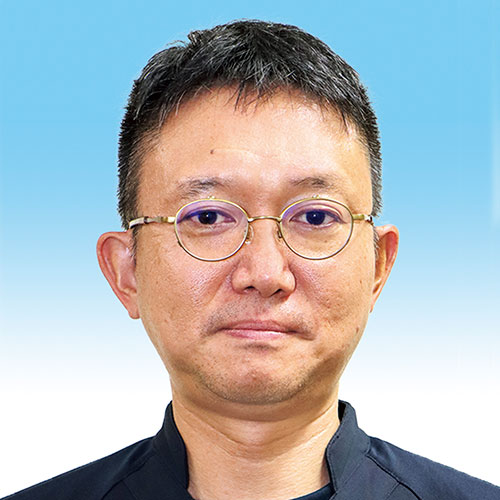
-
赤津 智也
上士幌クリニック 副院長
対象疾患及び治療法について
対象疾患
1)狭心症、心筋梗塞
循環器内科で通院されている患者さんが最も多い疾患です。主に心臓の血管の動脈硬化が原因で発症する病気です。動脈硬化は血管の加齢現象ですので、超高齢化社会を迎えている日本においては、高齢者の増加に伴い、罹患する人数も増えてきています。特に若い頃から高血圧症、高脂血症、糖尿病、喫煙などの動脈硬化の促進因子があると、病気になる確率が高くなります。カテーテル治療、手術治療などを行った後でも、これらの動脈硬化促進因子の管理をしてゆくことが大事な疾患ですので、地域の先生を含め、一生病気と向かい合ってゆくことが大事です。
2)不整脈
不整脈疾患は症状、年齢、実に様々です。若い方でも不整脈の発作をもっていることもあれば、不整脈があっても症状も全くない方もいます。そのため、治療も、治療の必要ないもの、投薬による治療、カテーテルによる治療、植え込みデバイスによる治療など、実に様々で、患者さんの状態に合わせて治療が選択されます。
当院は不整脈専門医が常勤で勤務しており、不整脈のあらゆる疾患へ最新の治療が受けられる体勢が整っております。
動悸、ふらつきなど気になる症状のある方、症状が無くても健診で受診指導された方など、気軽に受診して頂ければと思います。
植え込みデバイス治療を受けておられる方は、今後、不整脈専門医によるデバイス専門外来を開設し、管理してゆくことを考えています。
不整脈について詳しくはこちらへ
3)心不全
超高齢化社会を迎えており、日本は今後心不全パンデミックを迎えると言われております。
心不全とは心臓病の最終形態です。動脈硬化、不整脈、弁膜症、心筋症、高血圧症、あらゆる疾患が原因で心不全状態になります。高齢者の数が増えれば、様々な疾患をもつ人が増えるので、当然心不全患者は今後爆発的に増加する可能性があります。
心不全はあらゆる疾患が原因となるため、心不全治療も人それぞれ治療法が違ってきます。そのため、個人個人しっかりと診察することによって、その人にとって一番最適な治療法を考え、地域ぐるみで管理ができるような体制を整えたいと考えています。
4)弁膜症
以前はリュウマチ熱による僧帽弁狭窄症という弁膜症が多かったのですが、リュウマチ熱の減少と、高齢化による動脈硬化性疾患の増加を背景に、大動脈弁の動脈硬化による狭搾症が非常に増加してきています。心臓超音波検査などで重症度の評価を行い、最終的には心臓血管外科での手術治療を検討することになります。
5)動脈瘤
主に胸部、腹部の大動脈が高血圧、動脈硬化により風船のように膨らんでしまう状態です。
破裂するまで自覚症状が無いことがほとんどですので、何かの検査の時に偶然発見されることが多いです。手術適応になるまでは、動脈硬化危険因子の十分なコントロールをすることが重要で、手術適応になったときには、手術治療か、最近はステントグラフト治療を選択することができます。現在当院ではまだステントグラフト治療は対応していませんが、今後治療ができる体制を整えてゆくことを考えています。
6)閉塞性動脈硬化症
動脈硬化により足の血管の血流が悪化し、歩行時に足が痛くなる症状が出現してきます。これも狭心症などと同様、動脈硬化が原因となりますので、動脈硬化危険因子の管理が重要になります。CT検査で動脈硬化の部位、重症度を検討し、カテーテルによる治療や手術による治療について検討することになります。この病気も治療した後に動脈硬化の危険因子の管理が大切ですので、地域ぐるみで管理が必要になります。
7)心筋症
心筋症も様々な病態が有り、特に治療を必要とせず、経過観察で良いものもあれば、十分な治療を必要とするものまで、様々です。そのため、一人一人しっかりと検査させて頂き、その人にあった最適な治療を選択してゆくこととなります。
8)静脈疾患
血栓性静脈炎、下肢静脈瘤といった疾患に対しても、下肢エコー検査、薬物治療などを行います。下肢静脈瘤に関しては、心臓血管外科にて手術治療を検討します。
当院では人工透析治療を行っていますので、心臓血管外科による透析用シャントの造成、シャントのトラブルに対する血管形成術などにも対応しております。
【関連する診療科】
【参加している研究など】
- カテーテルアブレーション全国症例登録研究[J-AB2022](詳しくはこちら(PDF))
- カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト(J-ABレジストリ)(詳しくはこちら(PDF))
- 新規我が国における心臓植え込み型デバイス治療の登録調査(New JCDTR)(詳しくはこちら(PDF))
- リード抜去症例の実態調査(J-LEXレジストリ)(詳しくはこちら(PDF))
- レセプトおよびDCPデータを用いた循環器疾患における医療の向上に資する研究(詳しくはこちら(PDF))